東京被爆二世・三世の会(おりづるの子) 会員の多様な要求を見すえて
ともに歩いた国民平和大行進
「東友」487号(5月号)1面の記事にあるように、2025年5月6日の「国民平和大行進」の出発集会では、被爆者のみなさんのスピーチに続き、東京被爆二世・三世の会(おりづるの子)の青木克明会長をはじめ参加した会員が紹介されました。
この日は、被爆80年を機に、被爆者とともに核兵器廃絶の運動をいっそう広げていこうという被爆二世・三世の決意の場ともなりました。

総会で話し合い深め
5月25日、おりづるの子の年次総会を開催しました。家島昌志東友会代表理事には、「ノーベル平和賞の意義を学びともに核兵器廃絶の運動を」と題して講演していただきました。今日の緊迫した核の危機という世界的視野をもって被爆者運動と平和賞の意義を理解することができました。氏は同時に、こうした運動を担う被爆二世・三世の役割の重要性を強調されました。
総会での話し合いを含めて、被爆80年の2025年に取り組むことのいくつかを紹介します。

会員の多彩な活動を大切に
当会の会員はけっして多くはありませんが、みなさん被爆二世であることを意識して、多彩に社会的発信を行っています。「あの夏の絵」(広島市立基町高校をモデルにした青年劇場の演劇)の公演を広げる、地域のお寺での平和のつどいで講話、芸術と原爆を結びつけておこなう次世代への継承企画、広島の原爆体験にもとづく講談制作など、さまざまな会員の活動が寄せられています。会報46号には、会員の著作を2点紹介しました。
こうした会員一人ひとりの取り組みを大切なこととして共有し、おりづるの子としてさらに社会に発信していきたいと思います。
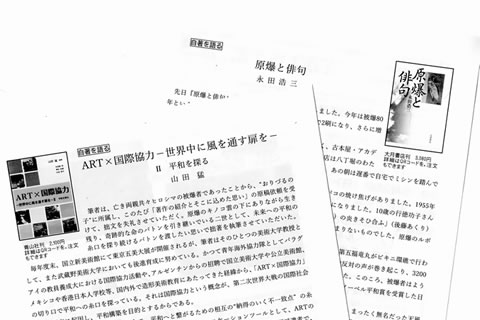
東友会とともに
おりづるの子の会員は、必ずしも各地区(ウェブページ作成者注:被爆者の「地区の会」のこと)とつながっているわけではありません。逆に日常、地区の活動をしている被爆二世のなかには、おりづるの子を知らない人もいます。しかし、「東友」の記事を見ていると、被爆二世・三世を会員として迎える地区の報告が増えてきました。
こうした地区、おりづるの子への所属の仕方も多様だという現状をふまえ、これまで以上に東友会の取り組みへの参加をおりづるの子会員に呼びかけ、そこに集う被爆二世と交流ができるようにしたいと思います。
総会では、東友会と東京生協によるヒロシマ・ナガサキパネル展(8月15日から24日)、各地の原爆展への参加、準備等への協力を呼びかけたところです。
9月28日の東友会とおりづるの子の共催企画である「被爆80年記念シンポジウム」には、たくさんの会員が参加するよう取り組みます。
被爆体験継承の課題
会員の中には、親や身内の被爆体験を絵本にしたり、読みものにまとめたりした人もいますが、被爆体験を詳しく聞く機会がこれまでなかったという人が多いようです。しかし、ここ数年、会として「体験の継承」をテーマにしてきましたので、具体的な取り組みにしていかなければならないと考えています。
総会に参加した会員の一人は、「親からわずかに伝えられた被爆体験を、現地訪問や実地踏査により避難の軌跡を追体験する、原爆を辛うじて生き延び戦後社会を駆け抜けた親たちの日常の言動のなかに原爆の影が見えなかったかなど注意深く振り返る、等々により被爆体験をより生々しく伝えたり、同時に被爆PTSD(心的外傷後ストレス障害)を認識したりできるかもしれません。それらによって被爆二世ならではの被爆体験の継承もできるのではないか」と語っています。
活動としては、たとえば「親の体験をまとめたい」と思っている会員が集まって、話し合いながら文字にしていく活動を始めてみようといった意見もあります。
